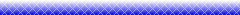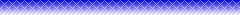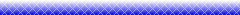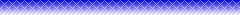SponsoredLink
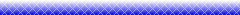
小児期崩壊性障害の現状
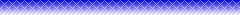
発達障害の中でも極めて重い症状があるとされているのが、小児期崩壊性障害(Childhood Disintegrative Disorders:CDD)で、小児期崩壊性障害について聞いたことのある人は、一般的には少ないのではないでしょうか。それもそのはずで、この障害にかかる人は極めて稀であり、発症率は10万人に1人とも言われています。
小児期崩壊性障害がどのような経過をたどるのか、少しご説明しましょう。この病気は先天性のものではなく、従って生後2歳くらいまでは正常な成長過程を歩む場合がほとんどです。大抵の場合、4歳前後で発症し、10歳までには症状が現れ始めます。
脳や神経系の感染症への罹患によって発症するとも言われていますが、原因はまだ明確になっていません。発症後の予後は悪く、治療法もないとのことで、一度発症すると完治することはまずありません。他の発達障害に比べても症状が重く、介助は一生涯必要不可欠となります。
崩壊性という病名が表すように、正常に発達してきた能力が、病気の発症後には退行していくのが特徴です。幼児痴呆やヘラー症候群とも呼ばれ、崩壊性精神病という別名もあります。
崩壊性精神病を発症すると、乳児期から少しずつ増えてきた言葉や単語が再び出なくなり、運動能力も低下することから今までできた遊びもできなくなります。またトイレトレーニングを終えていた子供でも、再び排泄コントロールができない状態に戻ります。
これらの能力の退行と並行して、発達障害特有のこだわりの強さや習慣的行動も見られるようになります。発症原因は分かっていないものの、前兆として感情の起伏が激しくなり、不安感が強まるなどの症状が見られるようです。
カテゴリのトップへ
トップページへ
Copyright(c)発達障害の現状と注意点